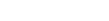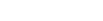PM・PLの心得: 認識ズレを防ぐコミュニケーションのコツ

プロジェクトを円滑に進めるためには「お客様の期待値をコントロールする力」も欠かせません。
期待と現実のギャップから認識のズレが生じると、手戻りや信頼関係の悪化につながることも。
今回は、私自身が実践している“認識ズレを防ぐ”のコツをご紹介します。
目次
はじめに
こんにちは。クラウドソリューション第二グループの namiki.m です。
私はこれまでAI関連プロジェクト、特にチャットボット導入案件に多く携わってきました。
私が社会人なりたてだった当時は第三次AIブームの真っ只中で、「AIなら何でもできるのでは?」という過度な期待を持つお客様も多くいらっしゃいました。
こうした背景から、プロジェクトを円滑に進めるには「できること/できないこと」を明確に伝える力が不可欠だと感じました。
その経験を通じて、お客様の期待値を適切にコントロールするためのコミュニケーションの工夫を意識するようになりました。
今回はその実体験をもとに、期待値コントロールに必要な「認識ズレを防ぐ方法」を紹介していこうと思います。
期待値コントロールとは
ここでいう「期待値コントロール」とは、
お客様が「このプロジェクト(またはシステム)で実現できる」と考えている内容やレベルを、現実とすり合わせて調整していくことを指します。
プロジェクトの初期段階では、システムの機能や成果物のイメージがふわっとしていることが多く、
お客様は「これくらいできるはず」と思っていたり、逆に「それができるなんて知らなかった」と感じることも。
そうした思い込みやズレをそのままにしておくと、後々「思っていたものと違う」という不満に直結します。
主に以下のような点をお客様と丁寧にすり合わせ、認識ズレを無くしていくことが重要です。
|
認識ズレにより起こり得る問題
お客様との間で認識にズレがあると、プロジェクトは早い段階でつまずきやすくなります。
特にAIやITシステムのような専門的な分野では、技術に対する認識の差がトラブルの種になり兼ねません。
「この機能は当然あると思っていたのに、実装されていない」
「全部自動でやってくれると思っていたのに、結局手作業が必要だった」
こうした声が挙がると不満が蓄積され、お客様との信頼関係の悪化にもつながります。
また、過度な期待がプロジェクトメンバーに無理なプレッシャーとして降りかかることで、
メンバーが疲弊し、スケジュール遅延や品質低下を引き起こすこともあります。
本来、避けられたはずの手戻りや仕様変更に追われる状況は、チームだけでなくお客様にとっても大きな損失です。
その原因の多くが、「最初にちゃんと認識をすり合わせていなかったこと」だったりします。
こうした問題を防ぐためにも、PMやPLが期待値を調整し、現実的なラインを明確に伝えていくことが重要です。
お客様との認識ズレを防ぐポイント
では、どうすれば認識ズレを防ぎ、お客様の期待値コントロールをしながら円滑なプロジェクト推進ができるのでしょうか。
ここでは日々私が心掛けている「認識ズレを防ぐポイント」を3つご紹介します。
① 期待値のすり合わせを徹底する
例えば、お客様が「AIなら何でもできる」「システムを作ればすぐ解決する」と思っている場合、それが前提になったまま話が進むと後々トラブルの原因になります。
「できること/できないこと」や「制約条件」を具体的に説明し実現可能な範囲を明確にすることで、早い段階で誤解を防ぐことができます。
② 相手のリテラシーに応じた説明を心がける
技術的な話をそのまま伝えても、お客様によっては理解が難しいこともあります。
専門用語を避けて業務に沿った具体例を使ったり、図解やワイヤーフレームを活用することで、お互いのイメージのズレを小さくできます。
「技術を伝える」のではなく、「相手に伝わる表現を選ぶ」ことが大切だと思っています。
③ 定例会議+カジュアルな場を設ける
定例会議での進捗確認だけでなく、SlackやTeamsなどを使って日常的に気軽なやり取りができる状態を作っておくと、小さな認識の違いや不安を早めにキャッチできます。
雑談の中から本音が出ることも少なくありません。カジュアルな場を意識的に活用することで、信頼関係も築きやすくなります。
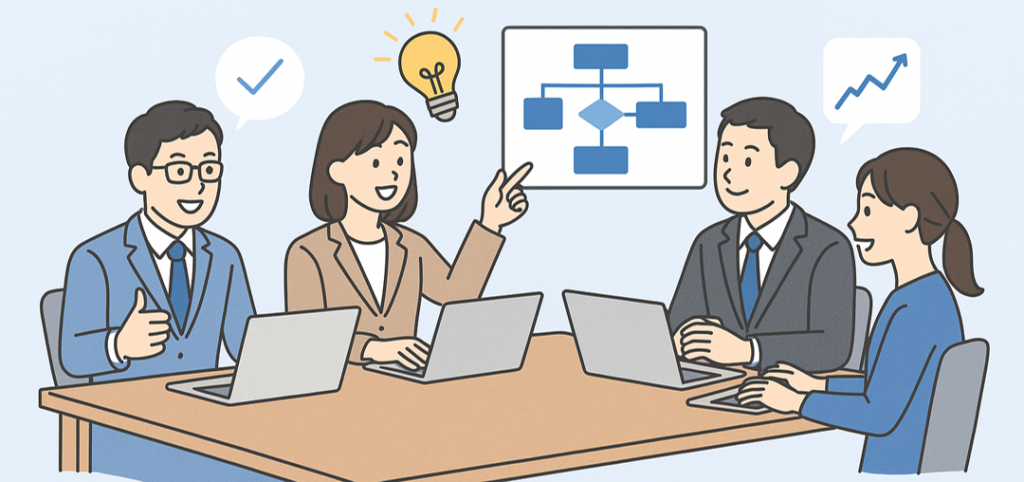
この3つのポイントを意識するだけでも、お客様とのコミュニケーションの質は変わると思います。
認識のズレを防ぐことは、結果的にチームの負荷軽減やプロジェクト全体の成功にも直結します。
まとめ
今回は、お客様との認識ズレを防ぐポイントをご紹介しました。
特にAIやITシステムのような専門性の高い案件では、お客様との期待値のギャップが大きなトラブルに繋がり兼ねません。
だからこそ、「できること/できないこと」を丁寧にすり合わせる期待値コントロールが重要です。
相手のリテラシーに応じた説明、日々の細かなコミュニケーション、誠実な対話が信頼関係の土台になると思います。
そして最後に、個人的に強調したいことはPMやPLは“YESマン”であってはならないということです。
何でも「できます」と言ってしまうのは一時的にはラクかもしれませんが、
その先にあるのは手戻りやプロジェクトメンバーの疲弊、そして(お客様やプロジェクトメンバーからの)信頼の喪失だと思います。
お客様にとって本当に価値のある存在とは、「何でも言う通りにする人」ではなく「現実を踏まえて最善を一緒に考えてくれる人」ではないでしょうか。
お客様と認識を揃えながら、プロジェクトメンバーを守りながら、
一歩一歩現実的なゴールに向かってプロジェクトを進めていくことがPMやPLに求められる大切な役割だと私は考えています。
この記事がこれからプロジェクトに関わるどなたかのヒントや後押しになれば嬉しいです。