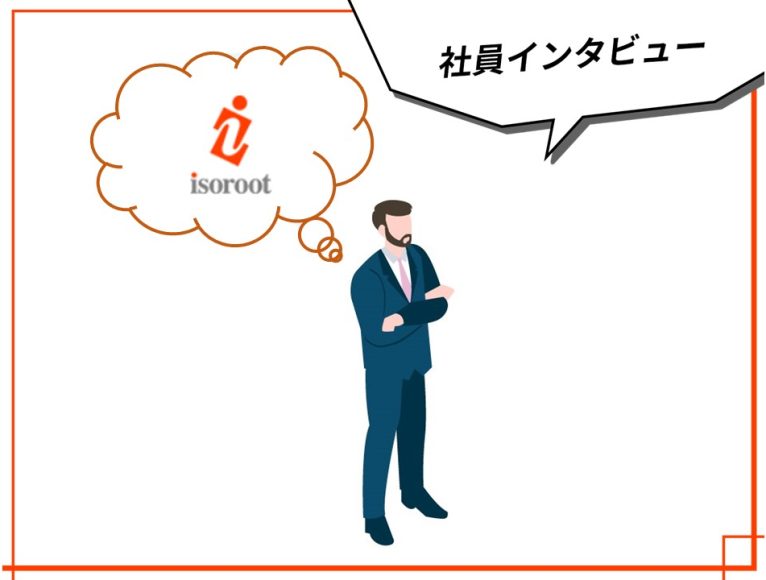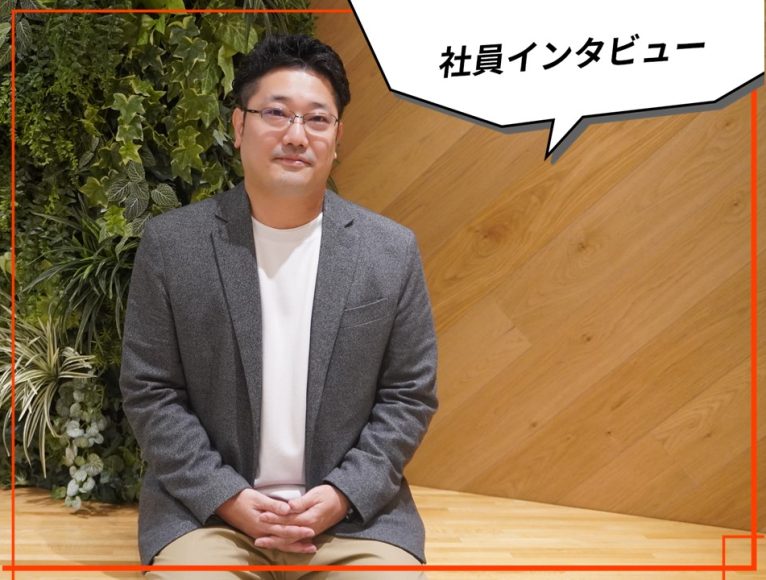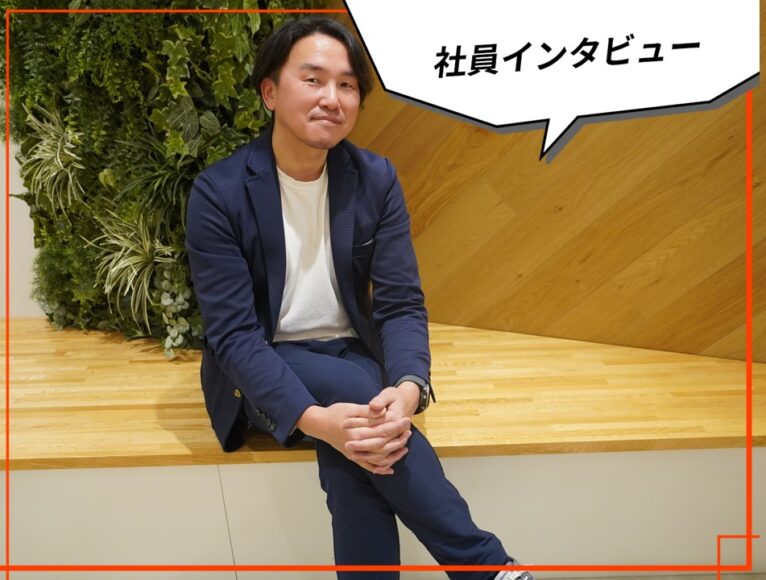チーム責任者インタビュー#22~「ビジネスを創造し最大の価値提供ができるフルスタックなエンジニアへ」~
こんにちは!キャリア採用チームの古田です。【自分の手でビジネスを生み出せる環境】や【はたらく社員の人柄】に惹かれて入社するメンバーが多いのが、アイソルートの特徴の一つです。そこで今回、各チームの責任者にインタビューを行い、アイソルートの第一線で活躍するメンバーの「これまでのキャリア」、「胸に秘めた熱い想い」や「チームの魅力」など、気になるところをたくさん聞いてみました。記事を通じて、皆さんにアイソルートの “リアル” をお届けしていきます!
今回は、この方です!

システムサービス本部 第4部
プラットフォームソリューション第2グループ 課長
K.I.さん/2006年入社
よろしくお願いします。まずはK.I.さんについて教えてください!
よろしくお願いします。出身は、茨城県ひたちなか市です。テレビとかで紹介されているネモフィラのひたち海浜公園が有名なところですね。趣味は麻雀、バイク、ゴルフかな。麻雀の腕はプロ級です(笑)Mリーグの選手と打ったこともあります。バイク歴は高1からなので、そろそろ30年になりますね。ゴルフはコロナが流行してからあまり行かなくなりましたが、それ以前は月一くらいでコースに行っていました。そろそろ復活させたいと思ってます。
アイソルートNO.1雀士との呼び声は伊達じゃないですね (笑)
では、そんなK.I.さんがアイソルートへの入社を決めた時の話について教えてください。
実は、大学卒業後は麻雀で身を立てようと考えていて、そっちを頑張っていたんですよね。ただ大学時代からPCやネットワークなど、ITにはずっと興味があったので、麻雀は趣味として続け、ITの領域で就職することを決めました。何事にも前向きな社員が多かったことに惹かれたことと、当時まだ設立6~7年目くらいの会社だったこともあり、「これから会社を大きくしていくぞ!」という意識がとても高かったので、アイソルートに入社を決めました。
そこから徐々に会社が大きくなっていき、制度やオフィスがアップグレードしていきました。入社当時は小さな雑居ビルの1室がオフィスでしたからね。人員拡大に伴いオフィス移転も何度かしていますが、今くらいの規模になった時には、とても感慨深かったです。会社拡大に対する想いも、未だに若い世代に受け継がれていて嬉しいですね。
そうですよね…オフィス環境や制度が整っていくことで、会社としての成長をよりダイレクトに実感できたのではと思います!では入社後から現在まで、どのような経験をされてきたのですか?
キャリアの最初はお客様先でサーバー、ネットワーク機器の監視運用をするメンバーから始まり、その後20人程度のチーム全体を統括する立場で監視サーバーの構築や運用までを経験しました。その次のお客様は大手SIerの研究開発部門で、新しい技術や機器の検証をしました。 そこで日本ではまだ名前が知られていないような早期の段階から、ネットワークをソフトウェアで制御するSD-WANの検証に着手し、動画などの大容量コンテンツを配信する場合やアクセスが集中した状況でも、Webコンテンツの表示と配信をスムーズにする仕組みとして運用するCDNの構築等を経験しました。それと並行して企業向けのネットワークやサーバー周りのシステム構築等を行いながら、現在のチームを立ち上げたという流れです。 現在は課長として、さらなる拡大を目指しています。
ちなみに、このアイソルート本社の無線整備は私ともう1名で行ったんですよ。天井や床への埋め込み作業が必要だったので、内装工事業者よりも早くに動き出して全社の無線LANを整備しました。管理は総務さんに託したんですけどね。内装工事業者の傍で、自分たちのオフィスが出来上がっていく様子を間近見ることができたのは、貴重な経験でした。
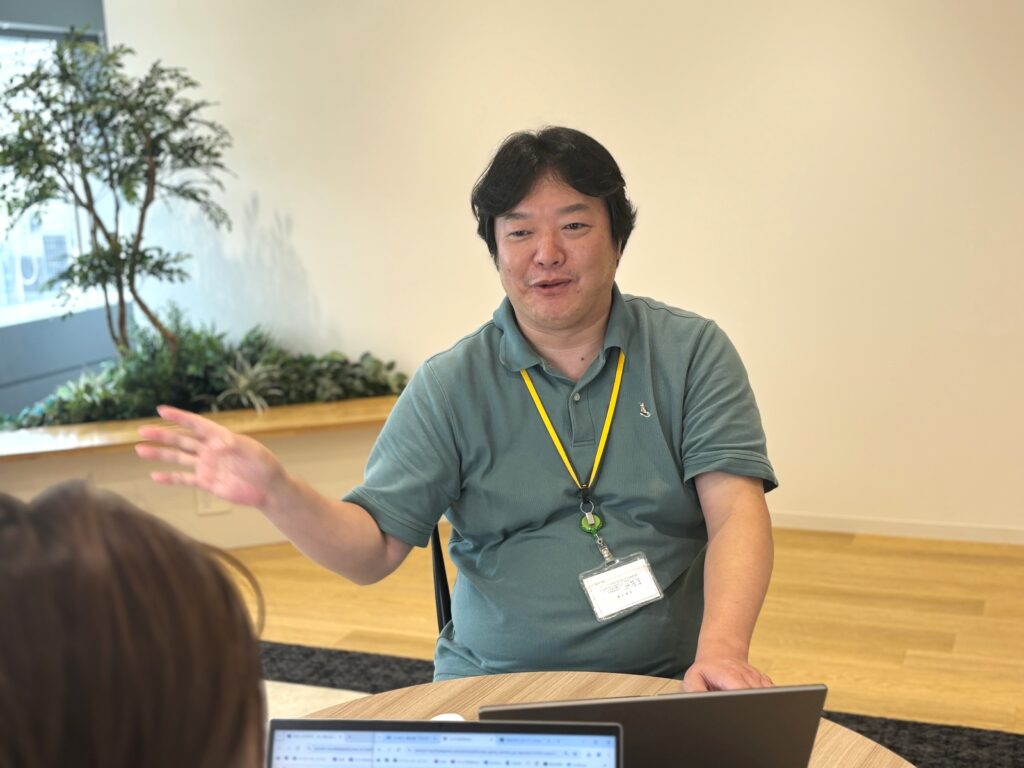
いつもサクサクなこのネットワーク環境があるのはK.I.さんのおかげだったんですね!改めて、ありがとうございます!
では次に、組織のメンバーについても教えていただけますか?
はい。私自身は複数のプロジェクトに関与していて、社員7名+パートナー社員15名程度のチームが組織のメンバーです。 一部現場での対応がある案件もありますが、今は案件対応がリモートで出来ることも多くなっていますのでリモートワークを活用しつつ、週1回はみんなと顔を合わせる機会を作っています。
メンバー達は明るく前向きな面々が多いです。基本、大きく3つくらいのプロジェクトに分かれており、みんなで会社に集まっても各自やっていることはバラバラですが、課会や部会等で意見交換をすることもあれば、出社時には一緒にランチに行ったり雑談したり、はたまた別案件を担当している人に自分の案件相談をしてみたりと、雰囲気はいいと思います。新人の教育なんかも複数の社員が週1回ほど予定を組んだりしていて、社員間の交流はかなり多いですし、皆、面倒見がよいと思いますよ。
今募集しているプロジェクトについては、リーダーのFさんは非常に技術力が高く、ネットワーク、サーバー、クラウド、プログラミングなど、すべてにおいて高いレベルで仕事をしてくれます。他のメンバーを引っ張っていってくれている存在です。かと思えばプライベートでは、毎年ねぷた祭りでハネトをやっているというアクティブな一面も持ち合わせているリーダーです。
Fリーダーをはじめ皆さん落ち着きがありつつ、個性豊かな方々が多いですよね!そのようなメンバーを率いるうえで、課としての目標は何でしょうか?
一言でいうと「営業も出来るエンジニア」になることです。我々はエンジニアでもありますが、1人のビジネスマンでもあります。 ビジネスマンは「自社の利益最大化」と「未来に向けた組織拡大」も求められますので、顧客に対して技術的な価値提供だけでなく、利益を最大化させるという観点で顧客との密なコミュニケーション、交渉やプレゼンテーションなどのスキルも必要になります。また会社を大きくしていくためには、自身のプレイヤーとしての活躍だけではなく、組織運営のスキルや後輩育成のスキルも必要になっていきます。
というところで、顧客に対して技術的な価値提供はもちろん、顧客の課題などを理解して適切な提案をしていけるような、顧客にとっても自社にとっても利益を生み出せるようなエンジニア集団を作っていきたいと思っています。
生成AIやロボットに仕事が代替されている中で、人にしかできない仕事で価値提供を続けるためにも、利益を生み出すコミュニケーションスキルは今後さらに重要になりますよね。エンジニアとしての「営業力」を磨くことができる組織なのだと理解しましたが、インフラエンジニアとして仕事をするうえでのやりがいは何でしょうか?
新しい技術や製品の検証をしていると、はじめから上手く動くことって基本的にほとんど無いんですよね。そこでサーバーの各種ログやパケットキャプチャを解析して根本的な原因を追究し、原因を取り除くことで機器が思った通りに動いたりするんですが、そういうときにはやりがいを感じますね。

あとは、システムが「ちゃんと動き続けているとき」ですね。インフラエンジニアはアプリケーションエンジニアのように表面上で動作するものを作るわけではないので、ちょっと地味な印象があるかと思います。ただ、システム全体の安定性や冗長性を設計したりするのは我々インフラエンジニアにしかできない大切な役目なので、何かシステムに障害等があった場合にもちゃんとバックアップ側のシステムに切り替わっていたり、安定した動作をしている状況に誇りを持ったりすることも多いです。
“インフラエンジニアとして”ではないですが、顧客理解を深め、顧客に対して適切な提案が出来て、それがビジネスとして成立した瞬間にはビジネスマンとしてのやりがいを感じることも多いですかね。 技術力+αの価値提供ができることはエンジニアとして、とても嬉しいです。
安定的なシステム稼働のために、誇りをもって仕事をされていると分かりました。ありがとうございます!では最後に、アイソルートに興味を持っていただいている皆さんに向けて、メッセージをよろしくお願いします!
現在私は1つの課を運営していますが、今後は規模を拡大し「部」へ昇格することを考えています。アイソルートでは、座って待っていたら「部」ができて、「はいあなた部長です」と任命されるような感じではなくて、自分たちで組織を拡大して「部としての体裁を保てる組織を創っていく」みたいな感じで組織拡大をしています。
そのような過程で、現在の「課」が「部」に昇格する時には、必然的に「課」や「係」というような組織が生まれますので、ゆくゆくはその組織運営をしてくれるような方が増えると嬉しいです。きっとその頃には、私が入ったころの50人規模から現在の180人まで拡大しているように、今の3倍くらいになっているのでしょうね。500人を超える会社になっていく未来は、当時の私は想像できていなかったです。
現在はインフラ、特にサーバーシステム、ネットワーク、クラウドの設計や構築をメインに行っていますが、最近はインフラ周りでもソフトウェアを使った柔軟な構成を構築することも多くなってきていて、ソフトウェアの設定というかチューニングをするためには開発言語を使いますので、今までのインフラだけでなくフルスタックなエンジニアを目指していただける環境も作っていきます。 また、先ほどお話したように、我々はビジネスマンでもあるため、技術を手段にビジネスを一緒に推進し、新たな道を創っていってくれる仲間を探しています。
一緒に働くことになった場合は、「モノづくりをするエンジニア」としてではなく「ビジネスマンとして」、もっと言い換えると「モノづくりを通じてビジネスを主導できるエンジニア」として!共に成長していきましょう!
ありがとうございました!