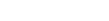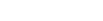生成AIがどのように活用されているか見てみよう 第2弾

生成AIを活用していこうという動きはIT関連の業界だけで起こっているものではありません。何年か前から推進の動きが盛んになっているDX化の波と合わさって、医療関係の業界や建築業界などそれまであまりITを取り入れてこなかった業界でも取り入れられている事例を目にする機会も増えてきています。
今回のアイキャッチ画像は「生成AIを活用しようとアイディアを巡らせている人」をChatGPTで出力してもらいました。
スペルミスやらあるのはご愛嬌ですが、やり取りを2,3往復しただけで割と良い感じのものが生成されてきました。
はじめに
こんにちは。クラウドソリューショングループのtakinami.sです。
生成AIの活用事例について前回軽く紹介させていただきましたが、今回もこんなアプローチが取れるのではないかと考えたものをいくつか挙げていこうと思います。
前回の記事はこちらからどうぞ。
この記事はアイソルートAdvent Calendar 2024の23日目の記事です。
活用事例
要約された文章の出力
Webページや各種書類を要約するといったことがパッと思い浮かぶのではないかと思いますが、最初から文章化されたものだけが対象ではありません。
例えば、OpenAIのGPT-4oモデルであれば、音声入力に対応しています。
ただ単に音声入力が可能なだけでなく、複数人での会話であれば何人が話しているかであったり、声のトーンであったりといった情報も認識可能となっています。
この機能を活かして、例えば会議を録音したデータを読み込ませることにより会議の要点のみをまとめた資料や議事録を出力するという使い方ができますね。
製品に対する問い合わせの電話のような感情が声のトーンに出やすいデータを集めておくことで、今までの傾向から相手の感情に合わせた端的な回答を生成してくれるといった使い方も考えられるでしょう。
もちろん、メールのような普通の文章になっているものを要約することも可能です。
最適な要約ができるようチューニングすることで、日々多くの文章を扱う職種においてメッセージを確認して要約する手間を省くことにつながります。
Azureのサービスページではアメリカの医療機関で導入された事例が取り上げられていました。
医療機関では個人情報を多数扱うかと思いますが、外部に漏れない設計ができていれば実用化することができるということも言えますね。
フォーマット化されていない文章の整理
「情報は共有してもらったけど、フォーマットを定めていなかったから確認に時間がかる」といった経験はございませんか。
一言で文書と言ってもその定義は曖昧なため、ファイル形式や書き方が統一されていないと結局欲しい情報に辿り着くのに苦労するというのは想像に難くないかと思います。
カラオケの『DAM』を手掛ける第一興商では、毎月自由形式で膨大な数が送られてくる追加曲のリクエストを生成AIに集計・分析させることで、業務効率化を達成したそうです。
曖昧な書き方をされている場合や誤字がある場合でもきちんと補正することができ、正確にリクエストを扱うことにもつながったようです。
問い合わせフォームを設けているサービスが多数かと思いますが、生成AIを導入することで上記のようにデータ分析をさせるだけでなく、よくある問い合わせへの回答を作成してもらうという使い方を組み合わせることが可能です。
最後に
活用できる部分がたくさんあるので、業界問わず導入検討のハードルが低くなれば良いなと感じています。
とは言いつつも、誰に使って欲しいか、どんな効果を期待しているのか、といった計画を事前に定めておくことはとても重要です。
そして、生成AIが得意としていること、逆に苦手としていることを理解をした上で正しい使い方をしなければなりません。
前回の私の記事と併せて、この記事が改めて生成AIと向き合うきっかけになりましたら幸いです。